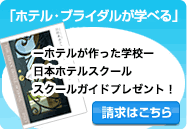サービスのクオリティを上げればコストはさがります(インタビュー後編)

高野 登 氏
ザ・リッツ・カールトン・ホテル 日本支社長
(インタビュー後編)
74年日本ホテルスクール卒業。
≪後編≫
リッツ・カールトン初代社長の情熱

高野さんがリッツ・カールトンの初代社長であるホルスト・シュルツィ氏と初めて会ったのは87年のベルリンだった。シュルツィ社長の握力の効いた握手を右手に感じながら「いつか、この人と一緒に仕事をするだろうな」という確かな予感を抱いていた。その予感が現実のものとなるのは3年後。高野さんがザ・リッツ・カールトン・サンフランシスコの開業に携わることになってからである。
リッツ・カールトンの源流そのものともいえるシュルツィ社長とは、どんな人物だったのだろうか。
「ひとことで言えば、とても優しい人でしたよ。自分の会社のスタッフがつらそうに仕事をしているのが、彼には耐えられないんですよね。一緒にほかのホテルに行ったりすると、よく聞かれましたよ、『タカノ、うちのスタッフはここのスタッフより楽しく働いているよな?』とね」
スタッフが楽しく仕事をしている場面を見るのが大好きな社長だった。逆に楽しんでいないスタッフを見つけると、すぐに支配人のところへ飛んでいって問いただす。
「君のスタッフは楽しく仕事をしているかい?」
「はい。もちろんです」
そんな支配人のうわべだけの返答には、シュルツィ氏は納得しなかった。
「いや、フロントの○○は楽しんでいないよ。どうして気が付かないんだ!」
上司には部下を楽しい環境で働かせる義務があるというのだ。
「シュルツィは最前線のスタッフに優しく、マネジメントクラスの人間には厳しい人だったのではないでしょうか。ホテルの開業前などにはシュルツィ自らが現地に赴いて、そこのスタッフたちと語り合う場を設けていました。そんなときもシュルツィは総支配人に向かって言うんです。『みんなの前でクレドの精神について説明してみせなさい』と。総支配人の考えがブレていようものなら、烈火のごとく怒っていましたよ」
シュルツィ社長が、かけていた眼鏡を乱暴にはずして「もう一度だけ私が言うからしっかり聞くんだ。いいか、クレドとは・・・」と語りかける真剣な場面を見て、スタッフたちはいっそう身を引き締めたという。
「日本ではニュアンスが違うかもしれませんが、アメリカでは"You are evangelist !"つまり『あなたは伝道者のようだ!』と言うのは、尊敬を伴った賛辞なんですね。シュルツィはまさに伝道者でした。GEの元会長、ジャック・ウェルチ氏も言っていましたが、企業が何かを創造するとき、宗教的な結束力、強さは必要だと思いますよ」
コストと投資の感覚
さまざまなリッツ・カールトンの逸話を耳にするにつれ、疑問に思うことがある。疑問というよりは心配と表現したほうが正しいだろうか。多くの読者の方も、筆者と同じことを思っている方がいるのではないだろうか。すなわち、ものすごく簡単に言えば「そのやり方で儲かるのか?」ということである。
例えば、2000ドルの決裁権。リッツ・カールトンでは現場スタッフに2000ドルの決裁権が与えられている。これによって、まさに"真実の瞬間"にスタッフたちが強力な力を発揮するだろうことは想像がつく。しかし、多くの業界関係者はこう思わないだろうか。「そんなことをして大丈夫なのか?」と。
「よく、いろいろな人から言われますよ。『高野さん、20万円の決裁権なんて与えたら、うちなら2週間でつぶれてますよ』なんてね。恐らく外部の方たちの頭の中には、全従業員が毎日のように20万円をジャブジャブと湯水のごとく浪費しているイメージが浮かぶのでしょうね。でも、そういうことではありません。大事なことは、スタッフたちが提供するサービスの選択肢を狭めないこと、企業とスタッフとの信頼関係を確認し合う仕組みであること、さらには、この20万円はコストではなく投資であるとする考え方なのです」
ザ・リッツ・カールトン大阪で、こんなことがあった。ある東京の大学教授が講演旅行で来阪されホテルに宿泊した。チェックアウトを済ませ、新幹線に乗ってから気が付いたのだが、ホテルに眼鏡とその日の午後に東京の講演会で使う資料を忘れてしまったのだ。教授は慌てて新幹線の中からザ・リッツ・カールトン大阪に電話をした。
「眼鏡と資料を忘れてしまった。今日の夕方に東京で使う資料なんだ!」
電話を受けたスタッフは何と答えたか。事もなげに、こう言ったそうだ。
「はい、かしこまりました。それでは今すぐに新幹線で追いかけさせていただきます。東京駅でお渡しすることはできますでしょうか」
きっと、教授はその言葉に驚くとともに、ほっと胸をなで下ろしたことだろう。かくて、眼鏡と資料は大阪から飛んできたスタッフによって、東京駅で教授の手に渡ったのだった。
「その後の講演会で、その教授はリッツ・カールトンのことをさんざん褒めてくださったそうですよ。うれしいですね。新幹線で東京と大阪を往復しても3万円足らずですよね。3万円の投資で、どれだけの新規顧客を獲得したでしょうか。少なくとも、その教授自身はリッツ・カールトンのヘビーユーザーになってくださいましたよ」
この話を通して、高野さんはクオリティとコスト、そして収益に対するリッツ・カールトンの考え方を説明してくれる。
「クオリティを上げるとコストが上がると考える人が多いですが、われわれはそうは考えません。クオリティを上げれば上げるほど、下がるコストがあるわけです。例えばリッツ・カールトンは宣伝広告費をほとんど使っていません。各界の著名人の方々がリッツ・カールトンの"うわさ話"をさまざまな機会にしてくれるからです。もし、彼らの口コミの宣伝力をお金で買おうと思ったら、億単位の費用がかかるでしょう」
リッツ・カールトンはなにも、忘れ物をしたすべてのお客さまを走って追いかけるわけではない。宅配便という選択肢もあるだろうし、資料ならファックスすれば済むかもしれない。さまざまな選択肢のなかの一つが新幹線で追いかけるという行為であり、それがお客さまにとって最良の手段なのであれば、即座に採用できるシステムと環境があるだけである。
「でも、意外に思う方もいるかもしれませんが、現場のコスト意識は非常に高いのですよ。教育や研修の過程でかなり時間を割いてトレーニングします」
多くの業界関係者やリッツ・カールトンのファンによって"2000ドル"とか"20万円"という数字だけが独り歩きしてしまった感がある。しかし、それはスタッフたちのサービス手段を狭めないためのセーフティネットであり、やむを得ずそれが発動するときというのは、「コスト」ではなく「投資」として投入されるということなのだ。
ナパバレーのブドウ畑
ところで高野さんは以前から、カリフォルニアのナパバレーで、かつてのホテル仲間と一緒にブドウを栽培しているという話を聞いた。この取材の3日後には休暇をとってカリフォルニアへ飛ぶのだという。
「とにかくナパ・ソノマが好き、ワインが好きで始めた趣味みたいな畑ですよ。フェアモント時代の上司がパートナーなんです。数エーカーの畑で、レーベンウッドやマーカムといったワイナリーにブドウを卸しています。彼の家の裏庭に掘っ立て小屋があってね、僕らはそれを自分たちのワイナリーって呼んでるんですけど、科学の実験みたいにオリジナルワインも造っています。楽しいですよ」
なじみのレストランに自分たちの作ったワインを持ち込んで、仲間とわいわいやるのが楽しいのだそうだ。
「今年のナパは冷夏で心配したのですが、9月中ごろから一気に気温の高い日が続いたので、とてもいいブドウが採れました。うちの畑でも52万ドルくらいの売り上げにはなったようです。そこから諸経費がたくさん引かれますから、ブドウ作りはビジネスとしては儲かりません。これはあくまで僕らの夢、ロマンのようなものです。とはいえ、収入源がいくつかあるというのは悪いことではないです。友人でもある作家の本田健さんなんかがよく言うんですよ。いつ会社がつぶれても驚かないくらいの経済的自由人になれって。でも、その域にはなかなか到達できませんね」
広がるリッツ・カールトンの精神

ホテルスクールを卒業してからすぐに渡米し、チャレンジ精神と行動力でアメリカのホテル業界を渡り歩いてきた高野さん。今の目標は何なのだろうか。
「最近、たまたま本などを出版させていただく機会をいただいて、たくさんの方から反響をいただきました。今朝も九州のある病院の院長先生と都内のホテルでお会いしまして、リッツ・カールトンのサービスと医療現場でのホスピタリティの重要性などについてお話ししたんです。こういう経験から思うのですが、今やあらゆる産業・業態がホスピタリティの実現を目指しています。その意味でもホテルに注がれているまなざしには、とても強いものがあるということです。今回、私の本に反響をいただいたということは、リッツ・カールトンというブランドが評価をいただいている証拠です。業界を超えて、リッツ・カールトンのホスピタリティの仕組みを紹介していくことは有意義である、と感じました」
リッツ・カールトンの本部にはリーダーシップセンターという教育機関がある。リッツ・カールトンのビジネスモデルとしての企業哲学、理念、成功の黄金律、ホスピタリティの仕組みを学び、将来のリーダーを養成する機関である。これをアジアに根付かせたいと高野さんは語ってくれた。
ホテル業界のみならず病院やメーカーまでが注目するリッツ・カールトンのホスピタリティ。従業員も顧客も幸福にする仕組みについて真剣に考える企業がアジアに増えることを願いたい。
(2006年取材)
高野 登 Noboru Takano
1953年生まれ。専門学校日本ホテルスクール(旧プリンス・ホテルスクール)卒業後、ニューヨークに渡る。ホテルキタノ、NYスタットラー・ヒルトンなどを経て、82年NYプラザホテルに勤務。その後、LAボナベンチャー、SFフェアモントホテルなどでマネジメントを経験し、90年にザ・リッツ・カールトン・サンフランシスコの開業に携わった後、リッツ・カールトンLAオフィスに転勤。その間、マリナ・デル・レイ、ハンティントン、シドニーの開業をサポートし、同時に日本支社を立ち上げる。93年にホノルルオフィスを開設した後、翌94年日本支社長就任。2009年同社退社。現在はホスピタリティを基にした企業活性化、人材育成、社内教育で指導・講演活動を続ける。ロングセラー『リッツ・カールトンが大切にする サービスを超える瞬間』(かんき出版)など著書多数。
トップランナーに学ぶ
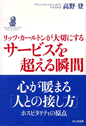
リッツ・カールトンが大切にする サービスを超える瞬間
高野 登/2005年/かんき出版
日本のみならず、世界でもホテルランキングで絶えずトップグループを保ち続けるリッツカールトンの秘訣を、現職の責任者が初めて公開する。お客様にリピーターになっていただくため、会社の信念(クレド)を具体的な仕事やサービスに結びつけるさまざまな仕組みを紹介している。