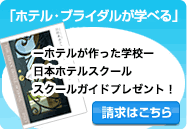リッツ・カールトンにホームランバッターはいません(インタビュー前編)

高野 登 氏
ザ・リッツ・カールトン・ホテル 日本支社長
(インタビュー前編)
74年日本ホテルスクール卒業。
≪前編≫
リッツ・カールトンのホスピタリティ
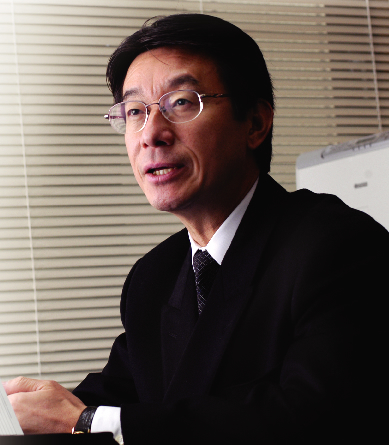
05年10月某日、東京・竹芝のホテル インターコンチネンタル 東京ベイの宴会場「ウィラード」には、300人を超える人がひしめきあっていた。皆、「宿屋塾」という勉強会の参加者である。
宿屋塾は「ホテル業界の将来を真剣に考える」というコンセプトでつくられた勉強会。月に1度の開催で、今回が65回目となる。筆者もずいぶんと以前から、幾たびとこの会に参加しているが、これほどの規模で開催されるのは久しぶりだ。通常は数十名の参加者が集う会で、それこそ勉強会という呼び名にふさわしい規模の会である。それが、今回ばかりはインターネットで告知をした後、たったの一日で参加予約者が100人を突破し、担当の近藤氏が泡を食って急遽会場をインターコンチネンタルに変更した。それでも、ホテル内で最も広い「ウィラード」の許容範囲いっぱいまでの人数が集まるまでにさほどの時間はかからなかったのだから、これは記録かもしれない。
今日の講演者は高野登さん。ザ・リッツ・カールトン・ホテル日本支社長である。皆、彼の話を聞きたいと、ここに集まったのだ。講演のテーマは「エンパワーメント」。トヨタのレクサスがよい例だが、ホテル業界のみならず他業界からも熱い視線を注がれるリッツ・カールトンのホスピタリティの礎石とはいったいどのようなものなのか。参加者の心は秘密の小箱の中身を見せてもらうようなわくわく感で膨らんでいた。
バントが打てるか
高野さんは講演台で語る。
「リッツ・カールトンは決してホームランバッターをつくろうとはしません。バントでコツコツかせぐ選手と組織をつくっているだけなんです」
リッツ・カールトンのホスピタリティマインドを語るときに持ち出される有名なエピソードがある。浜辺でプロポーズをしようと思った男性客が、スタッフに「ここにいすを一つ残しておいてくれませんか。後で彼女にプロポーズをしたいんです」と頼んでおいた。日没後にその男性客がフィアンセを伴って浜辺に戻ってきたときにはいすはもちろんのこと、純白のテーブルクロスを敷いたテーブルにシャンパンを置いて花びらを散らし、おまけに男性がひざまずいたときに服が汚れないようにと、いすの前にはタオルが敷かれていた。そして、プロポーズの舞台を完璧に整えたそのスタッフは、タキシード姿に着替えてほほ笑みながら二人の到着を待っていたという。
「この話を聞いて、『いやあ、リッツのスタッフはすごいなあ』という人もいるのですが、たいしたことではないんです。お金もかけていませんしね。種明かしをすると、そのスタッフはまず宴会係に頼んで、その日のパーティで使い終わった花をもらってきた。それからレストランに行ってワイン業者の方が試飲用に置いていったシャンパンを1本わけてもらった。最後にバンケットキャプテンからタキシードを借りて戻ってきた。ただそれだけなんです」
その"たいしたことではない"サービスに、2人の男女のお客さまは劇的に感動したという。だがしかし、高野さんはそのスタッフが決してホームランバッターだったわけではない、というのだ。
「みんながコツコツとバントを打った結果、点数が入ったのです。大切なのは、このバントを途切れずに打ち続けることです。先ほどの例で言えば、もし宴会係が花をくれなかったら・・・。もしレストランがシャンパンを分けてくれなければ・・・。もしキャプテンがタキシードを貸してくれなければ・・・。どこかが途切れていても、点数は入りませんでした」
大事なのはスタッフ全員がバントを打てる環境をつくっていくこと。そのためには、トップが明確なビジョンとミッションを強力なリーダーシップによって示してやらなければならない。
リッツ・カールトンというロケット
ホテルを開業させるということは、ロケットを発射するようなものだと高野さんは語る。ロケットは発射から大気圏を突破するまでに全燃料の95%を使い切ってしまうが、いったん軌道に乗りさえすれば、あとは残り5%の燃料で地球の周りを回ってくれる。ホテルも同じ。立ち上げのときにどれだけのパワーを込められるか、それにすべてがかかっている。
「大阪だって、最初から完璧なリッツ・カールトンだったわけじゃないんです。そりゃそうですよ。スタッフだって、いろいろなホテルから集まって来てくれているのですから、それぞれの土壌で培ったDNAを持ち込んでくる。そんな彼らに初代総支配人のジョン・ロルフスを中心とした幹部たちが、毎日毎日、それこそ耳にタコができるくらいにリッツ・カールトンの精神を語っていくことで、徐々に変わっていったんです。今だから言いますけど、ザ・リッツ・カールトン大阪というロケットが打ち上がって軌道に乗るまでには、開業から1年くらいかかりました」
クレドカードを手渡して、「はい、あなたはこれからリッツ・カールトンのスタッフです」と言っただけで本物のリッツマンになれる人などだれもいない。日々の業務のなかで、ロルフス総支配人とリーダーたちがリッツ・カールトンの精神について熱く語り続けた結果、全員が同じ価値観を持つに至ったのだ。
ザ・リッツ・カールトン大阪が開業して半年がたったころ、こんな出来事があった。
ディナータイムのメインダイニング「ラ・ベ」。そこに家族で食事をしているお客さまがいた。小さい男の子を連れたお客さまである。親たちは時間をかけてゆっくりと食事をするというぜいたくな時間を楽しむことができるが、子供にそれを強要するのは少し酷だろう。男の子もいつしかぐずりだしてしまった。泣きじゃくる一人の小悪魔によって、そのときの「ラ・ベ」の空気がいかなるものになったかはご想像のとおりである。
そんなとき一人のウエーターが思いたって1階のロゴショップに飛んで行き、大きなライオンのマスコット人形を抱えて帰ってきた。ウエーターは男の子に「ボク、しばらくこれで遊ばないかい?」と言ってそれを手渡した。ちなみにその人形、価格は2万円である。その機転が功を奏して、以後、男の子は人形を抱きすくめて、おとなしくしていたそうだ。一人のウエーターの機転によって「ラ・ベ」の空気は元に戻ったのである。
お客さまが驚いたのはその後である。食事が終わったあと、なんとウエーターはその人形を男の子に「どうぞ、お持ちください」とあげてしまったのだ。両親はとても感激したそうだ。次の日、この話を聞いたジョン・ロルフス総支配人は、そのウエーターを部長会に呼び出し、ほかのリーダーやスタッフの前で彼のしたことを褒めちぎった。
「これこそリッツ・カールトンのエンパワーメントだ! 私が毎日のように君たちに言い続けたこととは、こういうことなんだよ!」
そう興奮気味に話しながら30分もの間、ロルフスは皆の前で彼の頭をなでまわしながら褒めまくった。
それを見ていたほかのスタッフの頭に浮かんだ率直な感想とは、どんなものだったろうか。恐らくは「ああ、本当にここまでやってもいいのか!」というものだったのではないだろうか。
「大阪のスタッフの心にスイッチが入った象徴的な出来事だったんじゃないでしょうかね。もちろん30分もウエーターを褒めたのはロルフスの作戦ですよ。そうすることによって、スタッフの信頼感を勝ち取り、価値観を一本化していくんです」
スタッフが会社を心から信用しているか
リッツ・カールトンというホテルを開業して、それが軌道に乗るかどうかは一にかかって"スタッフが会社を信用しているか"なのだと高野さんは話す。
「例えば、この会社ではスタッフは内部顧客としてお客さまと同じように扱われますだとか、2000ドルまでの決裁権が与えられていますとか、そういったことを入社時に話しても、手放しに信用できる人なんていません。頭で分かっても心からは信用できないのです。例えば、先ほどのウエーターだって、総支配人に呼び出されたときは心のどこかで『2万円もする人形をあげてしまうなんて、何事だ!』と怒られるか、始末書のひとつも書かされるのでは、と思っていたでしょうね」
開業時、カンパニー本社から送り込まれた幹部たちは、スタッフに心の底からリッツ・カールトンという会社を信用してもらえるように心血を注いだ。「本当に2000ドルも使ったら、人事考課に響くのでは?」などという不信があっては、リッツ・カールトンの精神は根付かないからだ。
リッツ・カールトンの精神を浸透させるには"情熱を込めて毎日のように語る"という方法しかない。初めは部長クラスに浸透させ、次にマネジャークラスに浸透させ、最後に最前線のスタッフにまで浸透させていく。
「本社のスタッフたちが繰り返し言い続けていることは、リーダーであるあなたが情熱を最前線のスタッフに100%伝えようと思うなら、あなたは100では駄目だということ。情熱は伝えるごとに薄まるからです。最前線が100でいるためには、あなたは400でなければいけない。リーダーでいるということはそういうことです」
リッツ・カールトンの現場でリーダーであるということは、常にパッションを最大級以上に保って、スタッフたちにリッツの精神を訴え続けなければならない。これは大変なことだ。
確かな予感とともに
一つのプロパティを開業するのも、ロケット打ち上げなのだ。ホテルのトップに座る人間には最大級以上の情熱が求められる。では、リッツ・カールトンというブランドそのものが世に出て行くときにはどれほどのパワーが必要で、どんな人物がリーダーだったのだろうか。
リッツ・カールトン・ホテル・カンパニーが設立されたのは1983年である。高野さんはSFフェアモントに勤務していた88年に、ベルリンのコンベンションで当時の社長だったホルスト・シュルツィ氏に出会っている。シュルツィ氏は力強い握手をすると、高野さんにリッツ・カールトンの未来を熱く語ったという。
「話を聞いているうちに、ああ、自分はいつかこの人と一緒に働くだろうなあという予感がありました。プリンスホテルスクールを選んだときと同じ感覚ですよ。ああ、自分はこの学校に行くんだなとDMを見ただけで予感していましたから(笑)」
数年後、その予感は現実となり、高野さん自身がリッツ・カールトン・ホテル・カンパニーというロケットの重要な燃料になる日が訪れるのだった。
(2006年取材)
高野 登 Noboru Takano
1953年生まれ。専門学校日本ホテルスクール(旧プリンス・ホテルスクール)卒業後、ニューヨークに渡る。ホテルキタノ、NYスタットラー・ヒルトンなどを経て、82年NYプラザホテルに勤務。その後、LAボナベンチャー、SFフェアモントホテルなどでマネジメントを経験し、90年にザ・リッツ・カールトン・サンフランシスコの開業に携わった後、リッツ・カールトンLAオフィスに転勤。その間、マリナ・デル・レイ、ハンティントン、シドニーの開業をサポートし、同時に日本支社を立ち上げる。93年にホノルルオフィスを開設した後、翌94年日本支社長就任。2009年同社退社。現在はホスピタリティを基にした企業活性化、人材育成、社内教育で指導・講演活動を続ける。ロングセラー『リッツ・カールトンが大切にする サービスを超える瞬間』(かんき出版)など著書多数。
トップランナーに学ぶ
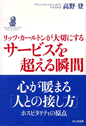
リッツ・カールトンが大切にする サービスを超える瞬間
高野 登/2005年/かんき出版
日本のみならず、世界でもホテルランキングで絶えずトップグループを保ち続けるリッツカールトンの秘訣を、現職の責任者が初めて公開する。お客様にリピーターになっていただくため、会社の信念(クレド)を具体的な仕事やサービスに結びつけるさまざまな仕組みを紹介している。